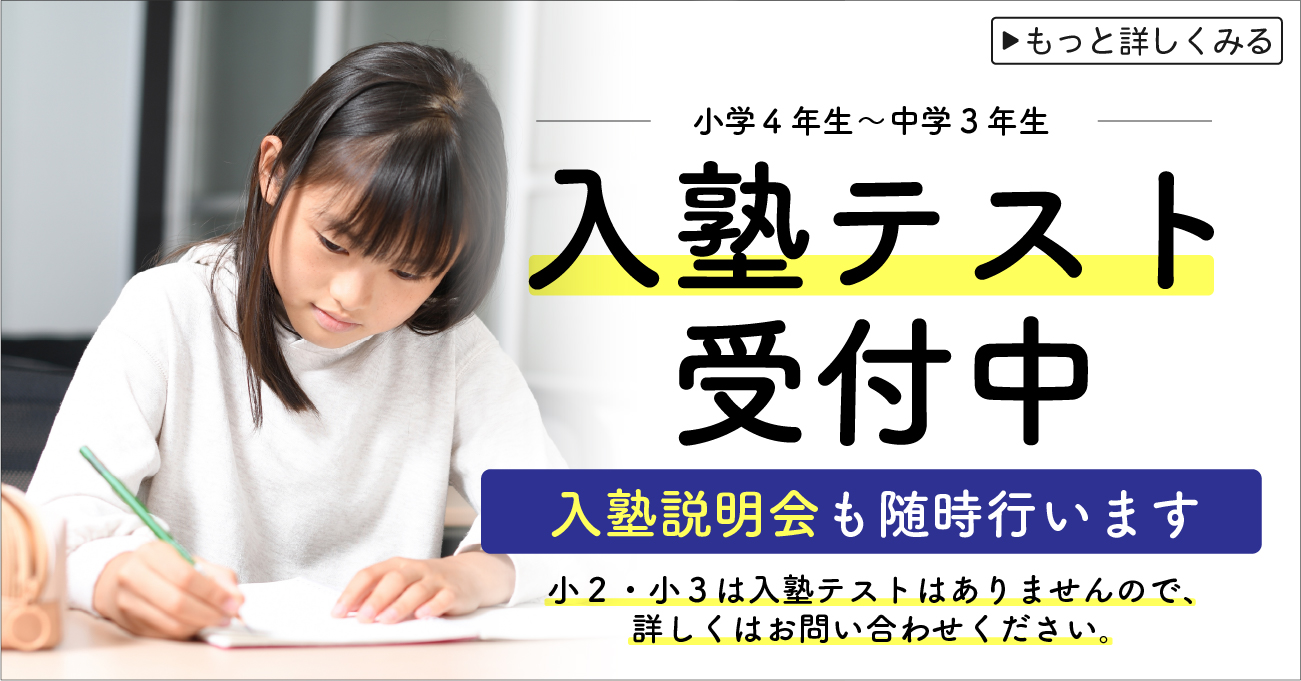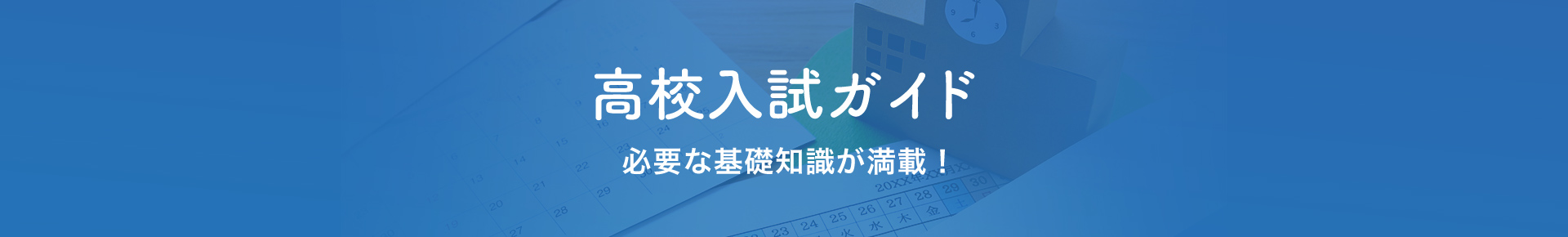
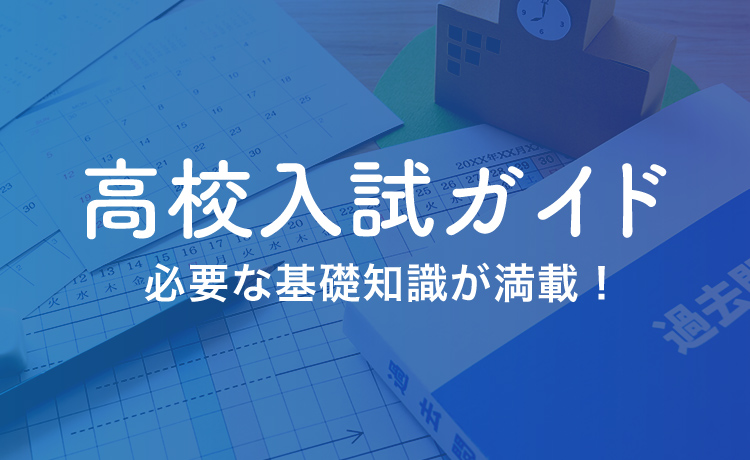

必要な基礎知識が満載!
受験突破に求められる国語力とは?
2025年度 大阪府公立一般入試問題分析と今後の受験に向けて求められる力(国語編)

・国語C(発展)問題
▶分析
昨年同様、1300字程度の論説文が2題・古文が1題・漢字や漢文の知識などの言語事項・作文の大問5題構成でした。2題の論説文は、ともに主張が明確に展開されている文章ですが、「思考と情報」「芸術について」といった抽象的な内容で、短時間で正確な内容理解には至らなかった受験生もいたのではないでしょうか。
古文は200字を超える長めの文章が出題され、筋を追う問題が中心となっていました。ただし、きちんと訳が取れていれば得点につなげられたでしょう。3問中1問が記述問題でしたが、これも訳を正確に読み取りそれをもとに記述すれば、正解できるレベルのものでした。
作文も例年通り、300字以内という字数条件で出題されています。提示された資料に込められた意図を読み取り、「日本語の特徴」について論じる、という論理的思考力や表現力が問われるものでした。普段から資料の意図を推察する練習をしていた受験生にとっては、比較的書きやすい出題であったと思われます。
特筆すべきは、昨年出題されなかった語句の抜き出しが復活し、計3問、90点中11点分の配点となっていることです。おそらくこの先も同様の出題がされるのではないかと予想されます。全体で記述は3問、22点と例年通り高めの配点となっています。記述の字数は最大で90字以内で、昨年よりも多めの字数です。文章の内容をまとめるものも出題されており、浅い読み取りでは正解が出ない設問が目立ちました。
▶求められる力
現代文では、難解な文章の要旨を正確に読み取る力、短時間で問題文の意図を理解して解く情報処理能力が求められます。選択肢問題も、各選択肢文自体の内容把握が必要となる難解なものですが、正誤を瞬時に見極められなければなりません。また、記述問題では、文章中から解答に使用できる箇所を素早く特定したうえで、必要な要素を取捨選択して指定字数内にまとめる力が必要です。一方で、古文・漢字や熟語の組み立てなどの言語事項は基本的な事柄が理解できていれば十分対応可能であったため、教科書内容の理解を疎かにせず、日頃から幅広い知識を身につけていくことが大切です。作文においては、普段から様々なことに関心を持ち、自分の考えを深めていくこと、資料やデータから本質を見抜く力、根拠を持って自分の意見を論理的に述べる力を身につけていくことが重要です。

・国語B(標準)問題
▶分析
今年のB問題は、1400字前後の論説文が2題・200字程度の古文・漢字・作文の5題構成でした。論説文はC問題よりもやや長く、「哲学」「建築」をテーマにした比較的難解な内容で、要旨および筆者の主張が読み取れているかを見る出題が中心になっています。対して古文は、文章こそ長めでしたが、物語調の読み取りやすいものでした。
論説文で最大55字以内の記述が出題され、古文でも25字以内の記述が1題出題されています。記述量は昨年よりやや減少したものの、空欄前後の言葉とのつながりを意識しながら必要な言葉をまとめる形式の出題が多く、そういった練習が十分でない受験生は苦戦したと思われます。一方、その他の問題・漢字などは基本的な内容を問うもので、教科書レベルの内容が理解できていれば無理なく解けたでしょう。
作文は昨年同様260字で出題されています。今年は、資料(グラフ)をもとに「読書の利点」について自分の考えを書くというものでした。複雑な条件もなく、しっかりと練習を積んでいれば書きやすいものだったと思われます。
▶求められる力
現代文では、本文の要旨を正確に読み取り、短時間で問題文の意図を理解して解く情報処理能力が求められます。空欄補充型の抜き出し問題では、文章内容をきちんと把握したうえで、空欄の前後を参考にしながら、本文の適した箇所を素早く探し出す力が必要です。一方、文法や漢字、漢文などの言語事項は基本的な事柄を問われるため、取りこぼしのないように、幅広い知識の習得を早くから意識して学習することが大切です。また、作文においては、自分の意見を論理的に述べられるよう、普段から自分の考えをしっかり持ち、それを表現する練習が必要です。